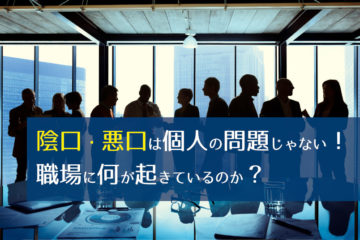「言われたことだけやれ」は正しいのか?

部下に対して「言われたことだけやっていればいいんだ!」と怒る上司がいます。
怒る場面にまで至らなくとも、部下の仕事の成果物について細かく点検して指摘したり、仕事の進め方自体にいろいろと口をはさむことがあるでしょう。
しかし、この「言われたことだけやれ」という考え方は本当に正しいのでしょうか?
詳しく検討していきましょう。
コミュニケーションの不完全性
まず確認しておかなければならないのは、コミュニケーションは常に不完全であるということです。
上司が部下に対してやって欲しいことを100%言い尽くすことも不可能ですし、部下が上司の言葉を全く誤解無く解釈することも不可能です。
このコミュニケーションの不完全性が存在する以上、上司の意図と部下の行動は絶対に一致することはありません。「言われたことだけやれ」というのは、そもそも不可能なのです。
なお、この不可能性をパワハラに利用する上司も見られます。その上司の心理とメカニズムについては別の記事で取り上げていますので、あわせてご覧ください。
参考:部下を潰す上司の心理
実務の細目まで上司が決めるべきなのか?
コミュニケーションの不完全性を指摘するとすぐに聞こえてくる反論は「いやいや、そうじゃなくて、指示の意図を察して行動して欲しいんだよ」といった類のものです。「気を利かせて」あるいは「行間を読んで」指示を受け取り、行動して欲しいというわけです。
しかし、そもそも実務の細かな点まで上司の指示通り、意図通りに部下が行動することが必要なのでしょうか? それは当事者である部下や上司、職場全体、会社全体にとって、はたして良いことなのでしょうか?
もちろん、業務の成果物について、細かく厳密に仕様が定められている場合もあるでしょう。しかし、当然ながらそうした業務については明確な仕様書が発行されるなどの対応が取られているはずですので、これから行う考察の対象にはなりません。念の為、書き添えておきます。
裁量の無い職場はストレスが溜まる
上司が部下の行う業務の細目まで決めることの問題点について、まずは個人レベルの影響から明らかにしましょう。
部下に適切に裁量が与えられていない職場がストレスフルであることは産業心理学の分野において1つの常識となっています。
厚生労働省が発表している「職場改善のためのヒント集」においても明確に、「少人数単位の裁量範囲を増やす」ことが推奨されています。
上司が部下に対して仕事を任せているにも関わらず、その仕事の進め方について干渉したり、成果物の非本質的な事項にまで「指示通り」を求めることは、部下のストレス要因になります。
ストレスがかかった部下の能率が下がることは、産業心理学的研究によって明らかにされていますし、それ以前に誰でも直感的に理解できることです。
上司が部下の行う業務の細目にまで口を出して実質的に裁量を奪うことは、部下のストレスを増大させ、生産性の低下や離職率の上昇を招きます。これは職場全体の士気の低下や、会社の利益を損なうことに繋がりますから、「それでも尚、指示通りに仕事をしてもらう必要があった」ことを上司が説明できない限り、細目への口出し行為は正当化されません。
有能なトップと無能なボトムの組織観
部下は上司から言われたことだけをやっていればいいという発想の根源には、「有能なトップと無能なボトム」の組織観があります。
最も重要な知識やノウハウを持っているのは組織のピラミッドの頂点に君臨する経営者であり、ピラミッドを下に降りるほど無能で「指導」が必要な人材になっていくという考え方です。
この組織観では、有能なトップの命令を大規模に実現する精密機械のような組織が望ましいということになります。ボトムはトップの手足となり、トップの意図通りに行動することで、最も優れたパフォーマンスを発揮することができるという前提で組織が構築されます。
こうした組織観はごくありふれたものです。近代における官僚制組織はこの前提に立つ組織の典型です。
有名な「テイラー主義」も「有能な管理者が無能な労働者のために作業標準を定め、業務のあらゆる工程を厳密に指定してあげることで、最大能率を達成することができる」という考え方です。
中間管理職の仕事とは?
この「有能なトップと無能なボトム」の組織観は、一見すると「言われたことだけやれ」という上司の言い分を支持するように思われます。
しかしながら、この組織観で有能なのはあくまで「トップ」だけであることを思い出す必要があります。いわゆる「上司」は中間管理職であり、有能であるとの前提が置かれる経営者ではありません。むしろ、どちらかといえば上司も部下も「無能なボトム」の側に入ります。
「有能なトップと無能なボトム」の組織観における中間管理職の存在意義は、トップのコミュニケーションコストの削減以外にはありません。
例えば、有能なトップ1人と平等で無能なボトム99人からなる100人の組織を考えましょう。すると、有能なトップは99人に対して指示を出す必要があり、大変なコミュニケーションコストがかかります。
一方、ピラミッド型の組織にして、1人の有能なトップの下に9人の中間管理職を置くと想定してみましょう。9人の中間管理職の下にはそれぞれ10人の部下が付き、この組織全体の人数は100人になります。
同じ100人でもピラミッド型の組織にすればトップは9人の中間管理職に対してのみ指示を出せばよく、それぞれの中間管理職も10人の部下に対してのみ指示を出せばよいわけですから、特定の個人に膨大なコミュニケーションコストを負担させることなく100人の組織を成立させることができます。中間管理職の層を増やせば、もっと大きな組織も運営できるでしょう。
「有能なトップと無能なボトム」の組織において、上司たる中間管理職の存在意義は単にこれだけのことに過ぎません。「有能なトップでも大きすぎるコミュニケーションコストは負担できない」という制約条件のもと、経営システム論的な計算の結果、存在意義が認められているだけのことなのです。
したがって、情報通信技術の進歩によってトップが直接指示を出せる人数の制約がなくなった場合、上司の存在意義もなくなります。現に「フラットな組織」論が流行すると、必ず中間管理職は無用のものとされ、糾弾の対象となります。
上記の議論から、部下に対して「言われたことだけやれ」と発言してはばからない上司は、自分で自分の首を絞めていることが分かります。
部下は言われたことだけやっていればいいという発想は「有能なトップと無能なボトム」の組織観に基づくものですが、その組織観は同時に「中間管理職はトップのコミュニケーションコスト削減のために存在するに過ぎず、情報通信技術が発達すれば不要になる」という結論を導きます。
「必要悪としての上司」という見方をする組織観を、その上司自身が「言われたことだけやれ」という発言で認めてしまっているわけですから、皮肉なものです。
自由な現場から知識創造が始まる
「部下は言われたことだけやっていればいい」という発想からは、抑圧的で停滞した組織の姿しか見えてきません。
むしろ逆の捉え方をすることによって、新たな組織観が開けます。つまり、「部下は自由にやればよい」という発想です。
新商品のアイデアや新たなノウハウなど、「イノベーション」あるいは「知識創造」は往々にして現場の自由な活動から生まれてきます。実務担当者の個人的な興味関心がきっかけとなって、時に社会に変革をもたらすほどの新たな知識が生まれるのです。
上記の考えは「有能なトップと無能なボトム」の組織観とは一線を画しており、ボトムである部下たちが自由に興味関心を追求することが奨励されます。
コミュニケーションの不完全性も、「部下に解釈の余地と裁量を与える」という意味で、むしろ肯定的な要素として受け入れられます。
この「知識創造企業」において、上司は部下が生み出したイノベーションの芽を選別し、これと見込んだ企画を実現するために経営層にかけあって必要な資源を調達するという、非常に重要な役目を担うことになります。
部下は上司の指示に従うことだけが仕事という狭い視野から抜け出すことが、柔軟でダイナミックな組織を作り上げるための第一歩になるのです。
参考文献
野中 郁次郎、竹内 弘高(梅本 勝博訳)(1996)「知識創造企業」東洋経済新報社